神経芽腫は、白血病や脳腫瘍に次いで多い小児がんで、副腎や骨盤などの腹部、頸部、胸部、骨盤部などから発生します。悪性度の高いものから、自然に小さくなっていくもの(自然退縮)など、さまざまな種類があり、高リスクでは、化学療法、外科治療、放射線治療を組み合わせた集学的治医療が必要となります。
JCCG神経芽腫委員会(JNBSG)とは、JCCG(日本小児がん研究グループ)のなかの神経芽腫のよりよい治療を考える研究グループです。
日本における神経芽腫の発症数は年間150-200人ほどと予想されますが、その中には、手術のみや比較的軽い治療で寛解可能なノンハイリスクから、非常に強力な集学的治療が必要となるハイリスクまでが含まれます。一つ一つの施設では経験が限られてしまうので、神経芽腫のより優れた治療法の開発のためには、多施設共同臨床試験が必要です。日本では、1980年代から全国的な共同研究が開始し、とくに高リスク神経芽腫に対して、厚生省/厚生労働省の研究班を中心に研究と治療開発が行われてきました。1985年から澤口班、1991年から土田班、1998年から金子班へと引き継がれ、治療成績は徐々に改善されてきました。また、これとは別に国内の各地域ごとのグループによる臨床研究や治療法の開発が行われてきました。しかし、欧米の小児がん臨床試験体制はその間に著しく整備され、大型の臨床試験を実施する基盤整備が進んでいました。さらに、新たな抗がん剤治療、免疫療法、分化誘導療法、幹細胞移植などの新規治療法が次々に導入されるようになり、21世紀においては大規模な臨床試験体制の基盤を無くしては更なる治療成績の向上を望めない状況となりました。
そこで、上記の厚生省/厚生労働省の研究班を中核に複数のグループが協力し合い、2006年に全国的な組織として日本神経芽腫研究グループ(Japan Neuroblastoma Study Group:JNBSG)が結成されることになりました。ここでは、神経芽腫に対する安全で有効な標準的治療法の確立と、より優れた新たな治療法の継続的な開発のため、各リスク群に対する臨床試験を計画・実施してまいりました。そして、2014よりJCCGが設立され、JNBSGは、JCCG神経芽腫委員会として活動を継続し、よりグローバルに活動を行っています。
田尻達郎前委員長の後任として、JCCG神経芽腫委員会委員長に就任しました、家原知子と申します。JCCG神経芽腫委員会は神経芽腫患者さんへのより良い治療提供を行うために、治療開発を行う目的で作られた研究者のグループです。
神経芽腫は手術のみや少量の薬物療法もしくは自然観察のみで治癒が期待できる低リスクの腫瘍から、腫瘍の増大や全身への転移をきたして、手術、薬物療法や放射線療法など様々な治療法を組み合わせて治療しないといけない高リスク腫瘍まで、様々なタイプがあります。小児の患者さんへの治療ですので、治癒を目的とするのみならず、副作用の軽減やその後の成長発達を考慮した、それぞれのタイプ(リスク)に応じた治療法の開発が重要となってきます。現在の標準治療は、過去の多数の患者さんの協力で行われた臨床試験の積み重ねで確立してきました。
私はJCCG神経芽腫委員会の委員長就任にあたり、以下の4つの目標を掲げております。
1.我が国における神経芽腫の患者さんの治療成績の改善およびQOL(クオリティ オブ ライフ;生活の質)の向上を目指した治療開発を行うこと
2.神経芽腫に関する科学的なエビデンスを創造し発信すること
3.神経芽腫の患者さんに情報発信や、治療開発を行うことで社会的貢献を行うこと
4.国際共同研究を推進すること
これらの目標を達成するためには、JCCG神経芽腫委員会のメンバーである専門家がその力を存分に発揮して、協働できる組織であることが必要です。また、科学的な視点を持って議論できる場を作り、次世代を担う若手研究者の積極的参加を促し育成を図って参りたいと思います。
今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
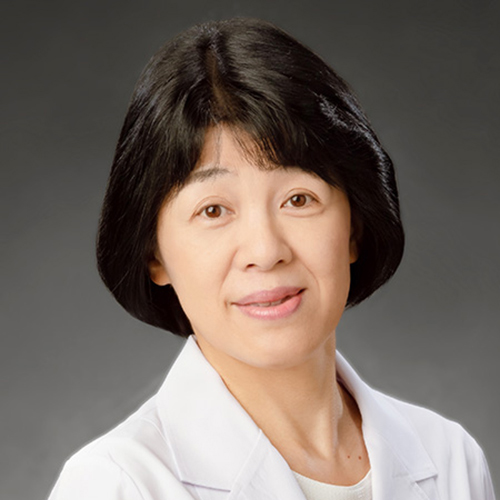
JCCG神経芽腫委員会 委員長
家原知子
| 2025年5月 | JN-H-25試験を開始しました。 |
|---|---|
| 2025年4月 | ANR2025において,JN-I-10試験の結果を発表しました。 |
| 2024年4月 | Pediatric Blood & Cancer誌にJN-H-11試験の結果が掲載されました。 |
| 2023年10月 | SIOP2023において,JN-L-10試験,JN-I-10試験の外科治療成績について発表しました。 |
| 2023年5月 | ANR2023において,JN-I-10試験の外科治療成績,JN-H-15試験の治療成績について発表しました。 |
| 2022年11月 | 第64回日本小児血液・がん学会学術集会において,JN-H-15試験の治療成績について発表しました。 |
| 2022年9月 | SIOP2022において,JN-I-10試験の外科治療成績について発表しました。 |
| 2022年1月 | JN-LI-21試験を開始しました。 |